大東流合氣柔術の形
「合気」修得の修業体系を取っています。
道進会は合氣の専門道場です。
武術の追求、正しい姿勢を身につけるよう稽古する。
心身の健康があればこその柔術を目指しています。
基本稽古で「氣の体」を作り「合氣」の稽古に入る。
基本稽古は力を全然使はない理合に基づく。
脱力を学びます。
武術とは力ではなく脱力によって向上します。
無理なき稽古なので老若男女を問はず修得可能。
大東流や合気道は合気揚げ(呼吸法)が
基本技である事はよく知られていますが、
当会では合気揚げを理解するための手助けとして、
「呼び戻し」「お化け手」「猫の手」等を稽古しています。
流祖 武田惣角

武田惣角は、武術家で宮相撲力士でもあった会津藩士・武田惣吉の次男として
現在の福島県河沼郡会津坂下町で生まれた。
若い頃から武術の修行に勤しみ、
小野派一刀流・鏡新明智流、宝蔵院流槍術、相撲、柔術などを幼少より学んでいる。
13歳の時、父を説得して上京した惣角は、直心影流の剣術家であり、
父の武田惣吉の友人であった榊原鍵吉(1830年〜1894年)に入門して内弟子になった。
ここで剣術の他、棒術、槍術、薙刀術、鎖鎌、弓なども学んだ。
10代後半のとき、兄の武田惣勝が若くして亡くなったことにより、
武田家を継ぐために呼び戻された。
しかし、惣角は家を飛び出して西南戦争の西郷隆盛軍に身を投じようとしたがかなわず、
西南戦争後は九州を皮切りに各地で武者修行した。
かなりの達人であったらしく「会津の小天狗」と賞される程の実力を持っていた。
一説によると、明治31年、霊山神社の宮司をしていた保科頼母より
「剣術を捨て、合気柔術を世に広めよ」との指示を受け、
剣術の修行を止めて大東流合気柔術の修行をしたという。
その後、武田惣角は全国行脚して大東流合気柔術の技法を教授し、
数多くの門弟を育てる。
明治31年以降については、英名録と謝礼録という記録が几帳面につけられているため、
いつ、どこで、誰に武術を教授したか、かなり詳細な記録がある。
武田惣角は生涯道場を持っての教授を行わず、請われれば何処にでも出向き、
年齢・出身・身分の差別無く大東流合気柔術の技法を広めた。
また全国行脚の最中に様々な他流試合やストリートファイトを行い、
大東流合気柔術の実戦性を証明した。
大正元年頃、惣角は北海道で再婚し、以後、北海道を本拠地とするようになる。
太平洋戦争中の昭和18年(1943年)に青森で客死、享年84。
筆記に難があったらしく、長文を書く際には門弟に代筆させていたという。
大東流とは
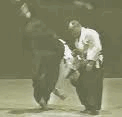
大東流は江戸時代御式内の名で会津藩上級武士、
藩士の護身武術として修業され、
江戸時代は門外不出とされていた柔術であります。
明治前半剣術家であった郷士武田惣角源正義先生が
家老西郷頼母の意を受けられ研鑚、
それに全国の武者修行で体得した武術と理合を加え完成されたのが
今日の大東流合気柔術であります。
明治31年頃より本格的に柔術家として活動を開始され明治、
大正、昭和と門弟3万余人と言われ、
陸海軍少将、中将級軍人から警察署長等、
裁判所判事にいたる多くの人材を育成された、
弟子の中には合氣道開祖植芝盛平氏、
八光流柔術宗家奥山龍峰氏、日本新英体道同主井上要一郎氏。
大東流にあっては高橋儀右衛門、松田豊作、吉田幸太郎、佐川幸義、
前菊太郎、堀川幸道、宗家武田時宗、佐藤啓輔、中津平三郎、阿久津政義、
大東流総主山本一刀斎角義など逸材を排出した。今日では多くの派、系統が全国的、
世界的に大東流系武術として発展されているのである。